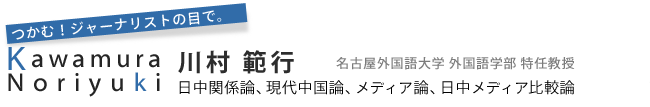中国《澎湃新闻》にインタビュー記事掲載
中国の武漢大学で 2025 年 7 月に戦後 80 年に関する国際シンポジウム
「抗日戦争勝利・世界反ファシズム戦争勝利 80 年」が開催され、日本から唯一、招聘講演をしました。
閉幕後に武漢大学歴史学院の博士課程に在籍する智敏さん、袁琦さんの両名から
“第二次世界大戦に於ける抗日戦争の位置づけ” “日本に於ける抗日戦争の研究”
などについて詳細なインタビューを受けました。
インタビュー内容は 8月22日に中国紙《澎湃新闻》 (電子版とも)に掲載されました。
以下は日本語訳文です。中国語原文は末尾URL。
日中関係学会副会長兼東海日中関係学会会長
「世界規模の視点から見た第二次世界大戦と中国の抗戦の物語
国民党と共産党の協力が抗戦勝利の鍵」
(原題: 「全球视野下的二战叙事与中国抗战|国共合作是抗战胜利的关键」
中国《澎湃新闻·私家历史》2025 年 8 月 22 日)
|川村範行:
インタビュー智敏、袁琦 (武漢大学歴史学院博士生)
2015 年 7 月 7 日、8 日、第二次世界大戦勝利 80 周年と中国の抗日戦争を記念する国際シンポジウムが武漢大学で成功裏に開催された。 会議中、国内外の専門家や学者は、第二次世界大戦関連研究の最先端の成果を積極的に共有し、長年の「西洋中心主義」から脱却し、第二次世界大戦の物語をグローバルな視点から書き換えようとし、過去には曖昧で無視されてきた歴史の声を提示しました。この会議を機に、「世界的な視点から見た第二次世界大戦の物語と中国の抵抗戦争」をテーマに、The PaperPrivate History は武漢大学第二次世界大戦史研究所と協力して、会議に出席した数人の国際学者にインタビューし、彼らの目に映った第二次世界大戦の研究と中国の抵抗戦争について話しました。
今回のインタビューのゲストは、名古屋外国語大学名誉教授、日中関係学会副会長、東海日中関係学会会長の川村範行氏です。

研究経歴について簡単に教えていただけますか?
川村範行 : 早稲田大学政治学科を卒業後、名古屋に本社を置く中日新聞社と東京本社で新聞記者として働いていました。 名古屋地区で発行される新聞の名前は「中日新聞」で、東京地区で発行される新聞は「東京新聞」と呼ばれる。
1985 年、新聞社から初めて中国に短期出張に行きました。 当時、私は中国語を知らず、「こんにちは」としか言えませんでした。 当時、江蘇省徐州市政府は愛知県内の都市と友好関係を築きたいと考えていました。 当時、徐州の人口は約 80 万人でしたが、愛知県には名古屋以外にこれほど大規模な都市はありませんでした。 そのため、日本側が検討した末、愛知県知多半島 10 都市が合同代表団を結成し、徐州に中国を訪問しました。 友好提携に関する交渉において中国側の通訳者は詳しい内容を通訳しませんでした。 そのため、私は自分で中国語を理解する必要性を痛感し、日本に帰国してすぐに中国語を学び始めました。 発の訪中で私は中国の広大な大地と悠久の歴史に惹かれ、将来は中国で報道の仕事をしたいと思っていました。
1995 年、私は新聞社から上海に赴任し、中日新聞・東京新聞上海支局長を務めました。 上海での 3 年間で、中国の様々な地域について学びたいと思い、30 回も出張し中国の各地を実際に知りました。 帰国後デスク、論説委員として活動。 その後、名古屋外国語大学と縁があり、2011 年に同大学に移り、教授として勤務しました。 私の専門は中国の政治・外交と日中関係です。 1993 年に名古屋に日中関係学会が設立され、私もすぐに入会し、30 年以上会員・理事を務め、13 年前に学会副会長に就任しました。
日本の学界における第二次世界大戦史の研究の現在の焦点は何ですか?
川村範行: 私は歴史学のバックグラウンドを持つ学者ではありませんが、この問題についてはある程度知っています。 第二次世界大戦に関する歴史家の研究には、主に次の側面が含まれます。
まず、第一に、第二次世界大戦勃発の背景と根本原因を研究し、戦争の本当の動機をたどり、日清戦争、日露戦争、第二次日清戦争を継続的なプロセスとして研究します。
当時、日本政府と軍の主な目的は、いわゆる「満州・モンゴルの権益」 (満蒙権益) 、つまり日清戦争や日露戦争を通じて日本が獲得した利益を守ることでした。日本国民の大多数も政府の中国政策を支持し、それが日中戦争の一因となった。しかし当時、戦争に反対する知識人や政治家もいた。
今日に至るまで、一部の日本の学者は、戦争を回避したり、休戦を達成したりする方法(政策や対抗策を含む)が可能だったかどうかを調べることを目的として、日中戦争の全過程を積極的に調査研究しています。代表的な学者の一人が、東京大学名誉教授の加藤陽子氏です。
第二に、日中戦争の実態と歴史的事実を研究することです。
一部の学者は、戦争勃発後、各地で起こった戦闘を研究し、当時の戦闘記録と兵士の証言(日本と中国の情報源を含む)をたどることに専念しています。これには南京大虐殺の研究も含まれます。研究の過程で、彼らは事実、文書、当事者の証言に頼ることを主張し、客観的かつ公正であるよう努めています。
第三に、戦後の処理と日本の遺留問題を研究することです。この分野は、主に領土問題、戦争賠償問題、戦後和解の 3 つの側面に関係する。
1. 領土問題: 初期の研究は、尖閣諸島(中国では釣魚島と呼ぶ) 、独島 (日本では竹島と呼ぶ)、および北方領土に焦点を当てていました。 日本の学者は今日までに、これらの問題について研究成果を発表し、独自の意見を述べています。
2. 補償問題:一部の学者は、韓国の慰安婦問題、中国人と朝鮮人の強制労働問題など、戦後補償に関する司法手続きの内容について懸念している。
3. 戦後和解問題:この問題は国民感情に関係しており、比較的解決が難しい問題です。
20 世紀 90 年代以降、一部の日本の学者は、国家指導者の謝罪や共通の歴史教科書編纂における両国の協力など、ドイツとフランスの戦後和解過程を積極的に研究してきた。 例えば、早稲田大学の劉傑教授は近年、「和解学」という新しい概念を提唱し、東アジア、特に日中関係における和解研究の推進を提唱し、関連する研究チームを設立しました。 彼は私の旧い友人です。
第四に、当時の日本軍の政策を研究する。 20 世紀の 30 年代から 40 年代にかけて、日本軍はますます強くなり、政府の権力はますます弱体化しました。 したがって、1931 年から 1945 年まで、中国の日本軍(関東軍)と日本の軍幹部が中国侵攻と戦争拡大に対してどのような戦略と見解を持っていたかが非常に重要だった。この点に関する情報を見つけることは容易ではありません。しかし、私の知る限り、自分の記録をつけたり、日記をつけたりする軍人・兵士もいます。従って、歴史家は新たに発見されたそのような情報に基づいて、より詳細な調査を行うことができます。
第五に、戦時中の日本の天皇の役割と行動。 数年前、昭和天皇の側近らが書き記した記録が日本の学者などに提供された。 したがって、歴史家は新しい情報に基づいて当時の天皇の言動をより正確に深く理解することができます。
日本の学者は、第二次世界大戦の歴史における中国の抗戦の地位をどのように見ており、どのような要因がそれに影響を与えたのでしょうか。
川村範行: 以前は抗日戦争の話をするとき、中日二国間戦争と見なしていたのが普通です。しかし、近年、学界に新たな視点が生まれ、第二次世界大戦の全体像の中で抗日戦争を検討し、第二次世界大戦における中国の抗日戦争の現状と役割を探求し始めています。
この新しい視点から、研究者は日中関係だけでなく、中国と米国との交流、中国と東アジア諸国との関係、中国と英国の外交関係にも焦点を当てています。 抗日戦争をより広い国際的文脈に置くこの研究の道は、現在の最先端の研究トレンドを表しています。
一部の西側諸国では、中国の抗戦の国際的地位を無視することがよくあります。 日本の学界はそれをどう理解したのでしょうか。
川村範行: 日本の学界では、第二次世界大戦において中国の抗日戦争は大きな役割を果たさなかったという見方が一般的です。 全体として、抗日戦争を第二次世界大戦の全局に統合するという見方はまだ普及しておらず、主流は依然として抗日戦争と第二次世界大戦を 2 つの独立した出来事と見なす傾向がある。したがって、日中戦争と世界戦争を結びつける学者の数は比較的少なく、このような統合的な視点は主流ではない。
中国の抗戦と第二次世界大戦が分離するきっかけとなった要因は何だと思いますか?
川村範行: 日本の学者の目には、ヨーロッパの戦場での戦争は比較的遠い紛争です。
したがって、抗日戦争とヨーロッパ戦場と密接な関係があるとは考えにくい。 当時の歴史的文脈では、日本の主な敵は中国であり、それは学者の研究観にも反映されており、ほとんどの人は抗日戦争を中国と日本の戦争と見なしていました。 したがって、ほとんどの日本の学者は、抗日戦争を研究する際に、それをヨーロッパの戦場、さらには世界戦争との相互接続の枠組みに入れないことがよくあります。 彼らは、 抗日戦争を第二次世界大戦全体の一部としてではなく、局地的な戦争として理解する傾向があります。
日本の学者は、抗日戦争における中国共産党の役割と役割をどのように見ていますか?
川村範行: それは良い質問ですね。一部の日本学者は、抗日戦争に対する国民党の貢献が主であり、特に長期にわたる大規模な正面戦場作戦と日米との外交交渉で国民党が中心的な役割を果たしたと見ている。同時に、彼らはまた、主に局地戦と広範なゲリラ戦における抵抗戦争における共産党の多大な貢献を確認した。ほとんどの日本の学者は、国民党と共産党の協力がなければ、抗日戦争に勝てないということに同意しています。したがって、国民党と共産党の協力(国共合作)は、抗日戦争の勝利の歴史において極めて重要な事実とみなされている。
第二次世界大戦という歴史問題における中国と日本の違いについてどう思いますか。
川村範行: 私の個人的な理解では、ほとんどの日本人は、第二次世界大戦に対する全体的な認識において、まだまだ「被害者心理」を持っている傾向があります。 多くの日本人にとって、第二次世界大戦の最も深い記憶は、人類史上初めて原爆が使用され、日本側に大きな被害を与え、日本社会に大きな影響を残した広島と長崎への原爆投下です。 今日に至るまで、このトラウマ的な記憶は多くの人々の感情の中に生き続けています。 また、第二次世界大戦後期には米軍爆撃機が頻繁に日本に飛んで主要都市を空襲し、国内のほぼすべての主要都市が爆撃を受けた。統計によると、米軍による攻撃は 200 以上の都市であり、日本国民の「戦争の被害者」という印象はさらに深まっている。
同時に、抗日戦争はほぼ完全に中国本土で行われたため、ほとんどの一般の日本国民は実際の戦場を見ることも、真に理解することもできませんでした。 さらに、当時の報道は日本軍によって厳しく統制されており、マスコミは戦争の真相、特に日本の侵略や南京大虐殺などほとんど公に報道されなかった。中国での大きな事件を真実に報道することができなかった。 その結果、人々は中国本土での戦争の事実についてほとんど理解していません。
「日本が中国に侵攻した」という基本的な内容は学校教育で学んできましたが、この部分の知識は浅く、具体的ではなく、個人的な感情に欠けていることがよくあります。それどころか、多くの日本の家庭では、戦争の記憶は主に両親や祖父母の証言から来ており、「原爆の犠牲者になった」とか「米軍の空爆で爆撃された」という経験を強調することが多いです。
もう一つの理由は、戦後に帰国した日本兵の多くが、戦争での経験を家族に話すことを躊躇することが多かったから、 家族は戦場でのを実態を知ることが出来ません。 それにもかかわらず、帰国後、自分自身を深く反省し、日記を書いたり、講演をしたりすることで、戦争で見たことや行ったことを日本社会に伝え、国民の反省を呼び起こすことを望んでいる人もいます。
では、中国と日本は、この歴史的認識の違いにどのように正しく対処すべきだと思いますか?
川村範行: 的確な質問です。私の論文(2015 年当時)では、中国、日本、韓国の学者が参加する大学レベルで歴史講義を設置するという重要な取り組みを提唱しました。 私はかつて、私が教えている大学に、日中韓三カ国の大学が共同で「日中韓合同歴史講座」を設立することを正式に提案しました。講座での講義の中心的な内容は、三国が共通して関心を持つ歴史的問題、特に現代における中国と日本、朝鮮半島と日本の関係です。例えば、1894 年の日清戦争勃発以来、中国と日本の間では一連の大きな歴史的出来事が起こった。 日清戦争の原因と結果、そして台湾が日本に植民支配された背景を明確に説明しなければならない。 1904 年の日露戦争は、日本が「南満州」を支配することに直結しました。また、1931 年の9.18 事変の原因と当時日本軍の陰謀も強調しなければならない。 朝鮮半島の立場で見ると、 日清戦争及び日露戦争以後、日本は徐々に半島に対する支配力を確立し、植民地化した、このような歴史
的背景も講義内容に含めなければならない。
このような日中韓歴史講座の開設により、三国の大学生が東アジア近代史について、客観性と公正性をよりオープンにして多元的な立場から学び、理解することができ、三国の相互理解と信頼を促進することができると考えています。
この取り組みは、日中歴史共同研究プロジェクトという成功した実践に端を発しています。振り返ってみると、両国政府の支援を受けて、2006 年から 2008 年にかけて最初の「日中共同歴史研究」が開始されました。この研究は、日中が共同で選抜した歴史家計約 20 名からなる共同研究チームが両国の歴史を議論するために実施した。これ自体が非常に難しい仕事です。
研究成果は、2010 年に日本の出版社から「日中歴史共同研究報告書」というタイトルで出版され、2 巻に分かれており、その第2 巻は近現代史の部分です。日中戦争の経過に関する章では、両国の学者の研究成果が「併記され」(つまり「日中双方の見解を並置して記述する」)、南京大虐殺などの主要な歴史問題についても同じアプローチが採用されたことは注目に値します。
日中の歴史研究の過程で、「両国の見解の並置」が正式に実現されたのはこれが初めてであり、これは大きな画期的な意義を持つ。
また、メディア報道についても私なりの見解を述べました。 現在、日本では毎年 8月 15 日頃、メディアは戦争関連の内容に焦点が当てられていますが、報道のほとんどは「被害者としての日本」の視点に焦点を当てており、主に原爆の被害者 (被爆者)や空襲の被害者などへのインタビューが中心です。 相対的に言えば、中国などの戦争で荒廃した国々の立場や声は、日本の主流メディアでは極めてまれである。 したがって、日本のメディアが戦争の歴史を報道する際には、戦争の犠牲者としての日本の歴史的記憶だけを強調するのではなく、戦争の全体像、特に被害国の立場と経験を客観的かつ公正に反映し、バランスの取れた視点にもっと注意を払ってほしいと思います。
(本文首发于《澎湃新闻·私家历史》。欢迎点击下载 “澎湃新闻”
方“阅读原文”即可访问全文。 )
中国語原文
https://mp.weixin.qq.com/s/d8wM7PTaCghNeFfdxBQ0bQ
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_31422084